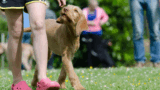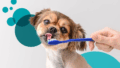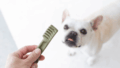「うちの子、なんでこんなに吠えるの?」
「散歩中に引っ張ってばかりで困る…..」
こんなふうに愛犬の行動に
頭を抱えた経験はありませんか?
犬は私たちの大切な家族
でも時には“困ったちゃん”になることありますよね
この記事では、よくある問題行動と原因について
やさしく解説していきます

犬の行動心理を知ろう!
犬の行動心理を知ることは
愛犬と飼い主様との信頼関係を築き
犬の心身の健康を守るために非常に重要です
以下にその理由をあげていきます
1.問題行動の理解と対処ができるようになる
吠える、嚙む、トイレを失敗するなどの問題行動は
犬のストレスや不安恐怖、欲求不満などが原因の場合があり
行動心理を理解することで単なる「悪い行動」ではなく
その背景にある感情や原因に対処できるようになります
2.効果的なしつけやトレーニングができるようになる
犬の学習方法や動機づけを知ることで
より効果的にトレーニングを進めることができます
犬にとって自然で理解しやすい方法で教えることで
ストレスを軽減しながら学習させられます
3.信頼関係の構築ができる
犬の感情やニーズに敏感になることで
犬は飼い主を信頼し安心して生活できるようになります
信頼関係が強まると呼び戻しや
指示にもよく従うようになります
4.ストレスや病気の早期発見ができる
犬は言葉で不調を訴えれませんが
行動や態度に変化が現れます
日常的な行動心理の理解があれば
いつもと違うサインに気づきやすくなり
早期に対処することができます
5.人と犬の共生社会の実現ができる
公共の場や他人との関わりの中で
犬が適切に行動出来ることはとても重要なことです
行動心理を理解してしつけることで
社会に適した犬に育てることが出来るのです
それが、不幸な犬を増やさないことにも繋がると思います
よくある愛犬の問題行動とは?
犬の問題行動とはどんな行動をいうのでしょうか
よく見られる問題行動を確認してみましょう
・無駄吠え
来客用や物音に対して延々と吠える
・噛みつき
本気で嚙みつく

・飛びつき
嬉しさのあまり人に飛びついてしまう
・散歩中の引っ張り
飼い主のペースを無視してグイグイ前へ行ってしまう
などがありますが、実は犬の問題行動の多くは
「ストレスや」や「欲求不満」が原因です
例えば
・十分な運動ができていない
・飼い主様とのコミュニケーションが足りていない
・怖い経験がトラウマになっている
・自分が”リーダー”だと勘違いしている などがあげられます
問題行動の心理とその対策
1.無駄吠え
・心理:警戒心、不安、退屈、欲求(遊んで欲しい、構ってなど)
・対策:無視、一貫した指示、運動や刺激の提供(散歩や知育トイなど)
2.嚙みつき
・心理:恐怖、攻撃性、遊び、歯の生え変わり(子犬の場合)
・対策:社会化の強化、落ち着かせる訓練(コマンド学習)、問題行動の予防
3.トイレの失敗
・心理:学習不足、ストレス、老化や病気
・対策:決まった場所、タイミングでの排泄習慣の形成、ポジティブな強化
4.引っ張り散歩
・心理:興奮、前に行きたい欲求
・対策:リードの使い方を学ばせる、落ち着いた歩行訓練
5.分離不安(留守番ができない)
・心理:飼い主への過度な依存、不安感
・対策:留守番に慣れさせるトレーニング、留守中の刺激(ラジオ、知育玩具など)
犬の行動心理の基本
犬の行動心理の基本を理解することは
犬とのより良い関係性を築くうえで非常に重要です
以下に犬の行動心理の基本的なポイントを
わかりやすく解説します
1.本能に基づいた行動
犬は先祖であるオオカミの本能をある程度引き継いでいます
そのため以下のような本能的な行動があります
・群れ(パック)で行動したがる⇒飼い主をリーダーと認識
・テリトリー意識⇒自分の縄張りを守ろうとする
・嗅覚を重視⇒匂いで情報を読み取る
・繰り返しの行動で学習⇒習慣が重要
2.社会性と順位意識
犬の社会性と順位意識(上下関係の認識)は
犬同士の関係性だけでなく、人間との関係を築くうえでも
非常に重要なポイントです
これらは犬が群れで生活していた祖先(オオカミ)
から引き継がれた本能的な性質です
🔹 犬の社会性の特徴
距離感の調整(相手が嫌がると下がる)
子犬の時期(特に3~14週齢)が社会化の
「ゴールデンタイム」他の犬や人、環境に慣れていないと
「怖がり」「攻撃的」になることがあります
・社会的行動の一例
あいさつの匂い嗅ぎ
プレイバウ(遊ぼうのポーズ)
距離感の調整(相手が嫌がると下がる
🔹 社会性を育むには
- 子犬期に多くの人、犬、音、場所に慣らす
- 他の犬との遊びや散歩中のマナーを教える
- 無理やり慣れさせるのではなく「楽しい体験」として学ばせる
学習と条件付け
学習とは
犬にとっての「学習」とは、行動と結果の関係を覚えることです
犬は「何をしたらどうなるか」を繰り返し経験し
その行動を増やしたり減らしたりしていきます
【古典的条件付け(パブロフ型)】
ある刺激(例:ベルの音)に、自然な反応(例:よだれ)を結びつける学習
例
ベルの音 → ごはん → よだれ
→ やがて「ベルの音」だけでよだれが出るようになる
犬が玄関のチャイム音で吠えるようになるのもこれに近い原理です
【オペラント条件付け(スキナー型)】
行動の結果に応じて、その行動の頻度が変わる
・「おすわり」したらおやつ
・引っ張ると締まるリードが、止まると緩む
・飛びついたら無視する、おもちゃを片づける
一般的には「ポジティブ強化」が最も効果的で、犬にも優しい方法とされています
学習のポイント
📌 一貫性が大事!
- 家族全員が同じ言葉・反応をすることが大切
- 「座れ」「おすわり」「すわれ」など表現がブレると混乱します
📌 タイミングが命!
- 正しい行動の直後1~2秒以内にご褒美を与える
- タイミングがずれると、犬は何に対して報酬が来たのかわからなくなります
📌 短く・楽しく・成功体験を!
- 1回のトレーニングは3〜5分でOK
- できたらたくさん褒めて、「やればいいことがある!」と学ばせる
感情の理解
犬は基本的な感情(喜び、恐れ、不安、興奮など)を感じますが、人間のような複雑な感情(嫉妬、罪悪感)は行動でそう見えるだけの場合もあります
主な感情行動
- 喜び:しっぽを大きく振る、飛びつく
- 不安:耳を伏せる、あくびをする(カーミングシグナル)
- 怒り:うなる、歯を見せる
- 恐怖:体を小さくする、震える、逃げる
カーミングシグナル(犬のボディランゲージ)
犬同士や人間に対して、自分の感情を伝えるための非言語コミュニケーションです
| 行動 | 意味 |
|---|---|
| あくびをする | 緊張の緩和・不安の表現 |
| 体を横に向ける | 敵意がないことのアピール |
| 鼻を舐める | ストレスサイン |
| ゆっくりまばたき | 安心・リラックス |
まとめ
犬の行動心理を理解することで
問題行動の予防・改善、信頼関係の構築が可能になります
犬は「人の言葉を完全には理解できない」代わりに
飼い主の態度、声のトーン、表情、行動を敏感に読み取っています
これらを理解することで愛犬との暮らしがより一層
楽しく、幸せなものになることでしょう